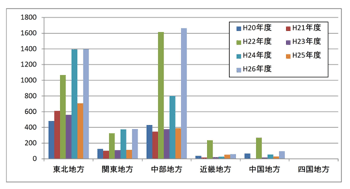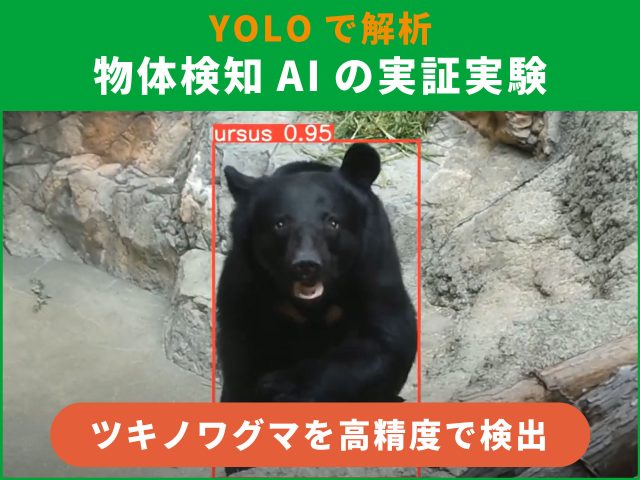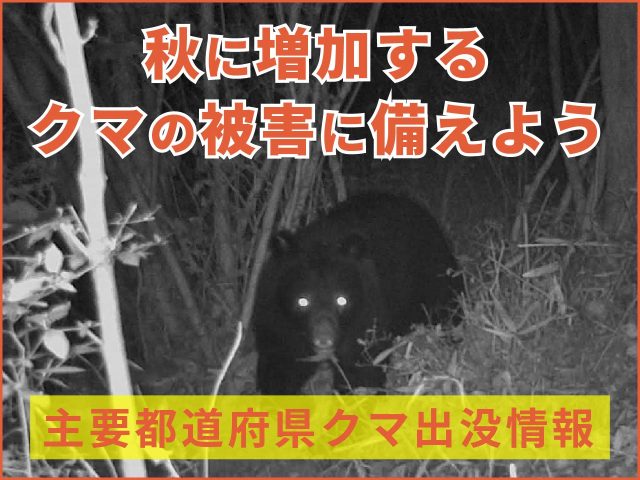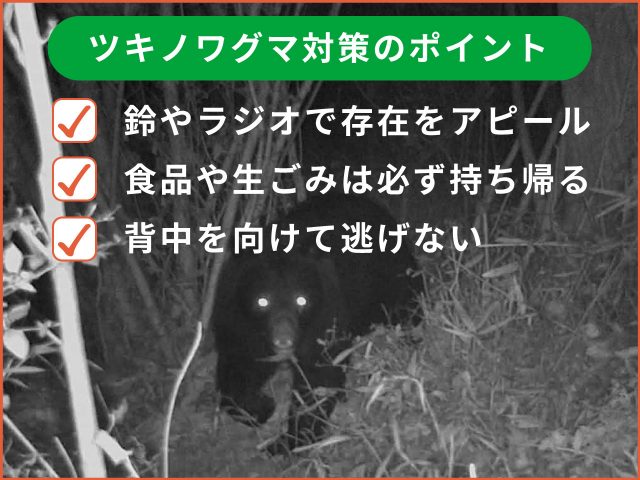投稿日:2025年8月27日
クマ被害に遭わないために
投稿日 : 2015年08月07日
更新日 : 2025年09月11日
こんにちは「鳥獣被害対策.com」の津田です。
今日の鳥獣被害対策の知恵袋は、クマのお話です。
日本には、本州と四国に生息する“ツキノワグマ”と、北海道に生息する“ヒグマ”の2種類がいます。
ツキノワグマは、体重70~120kg、頭からお尻までは120~145cmで、胸部に三日月形やアルファベットの「V」字状の白い斑紋が入るのが特徴です(希に、模様のない個体もいます)。
(ツキノワグマ)
ヒグマは、体重150~250kg、頭からお尻までは200~230cmと、ツキノワグマより大きく、林道で遭遇した方の話によると、ヒグマのことを「軽トラックが向ってくるようだった」と例えるほど、大きな動物です。
(ヒグマ)
ツキノワグマについて
このうち、今回は本州と四国に生息する“ツキノワグマ”についてのお話をします。
※九州にもツキノワグマは生息していましたが、最後の確実な捕獲記録は1957年で、既に
50年以上が経過しています。
そのため、平成24年に改定された“絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト”(環境省)では、九州におけるツキノワグマは絶滅したとされています。
また、記憶に新しい出来事として、今年5月に三重県いなべ市で捕獲されたツキノワグマの話があります。
この話は、イノシシ捕獲用の箱わなで錯誤捕獲されたツキノワグマを、滋賀県多賀町に放獣、その10日後に、放獣場所から南西側約6kmの場所で女性がツキノワグマに襲われ、大けがをしたというものです。
ただし、錯誤捕獲された個体と女性にケガをさせた個体は、鑑定結果によると、遺伝子型が異なるため、別個体であると判明しています。
このように、クマは他の大型動物と比較して、人身的な被害が発生することもあり、社会的に取り上げられることが多い動物です。
昨年(平成26年)は、ツキノワグマが大量に出没し、各地で問題となりました。
事前に大量出没が予想されていたにもかかわらず、100名以上の人身被害が出たそうです。
ちなみに、このツキノワグマの大量出没の予想ですが、どうやってできたのでしょうか?
実は、クマの餌となるドングリなどの結実量と関係があるようです。
一昨年(平成25年)は、ブナの当たり年で、各地でドングリが豊作となりました。このような年には、十分に脂肪を蓄えた多くの雌グマは、冬眠中に出産をすることができます。
しかし、昨年(平成26年)は、ブナの結実が悪く、不作となった地域が多かったようです。
つまり、一昨年は餌が十分にあって、出産も順調であったが、その翌年は冬眠前の餌が乏しく、親クマ・子クマともに空腹状態にあったことが想像できます。
そうなると、クマは餌を求めて、人里近くにまで出て来てしまい、ツキノワクマとの遭遇事故が多くなってしまいます。
環境省のホームページには、過去のクマ類の許可捕獲による捕獲数が公開されています。
昨年度(平成26年度)は、3,596頭のツキノワグマが捕獲され、このうち3,412頭が捕殺されています。
捕獲数と出没数はイコールではないものの、過去の捕獲数をみると、昨年度は一昨年と比較すると、多かったと言えます。
過去の許可捕獲数
- 平成20年度は1,145頭
- 平成21年度は1,081頭
- 平成22年度は3,513頭
- 平成23年度は1,085頭
- 平成24年度は2,651頭
- 平成25年度は1,292頭
- 平成26年度は3,596頭
(平成25年度(5月暫定値)は287頭)
図 ツキノワグマの捕獲数(許可捕獲数)
(環境省データを参考に作成)
https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs4/capture-qe.pdf
また、時期的特徴として、大量出没の年には、夏~秋にかけて人里への出没が増え始め、冬眠前の10~11月にかけて最も多く人里に出没することがわかっているようです。
地域によっては、里山が放棄されてツキノワグマの生息地が広がり、人間の住む場所との距離が近くなってしまったことが、ツキノワグマの大量出没の原因のひとつとなっています。
また、ある報告によると、ツキノワグマの生息分布域は、全国的に広がっているという見解もあります。
年によっては、これからツキノワグマの出没が多くなる時期になります。
ツキノワグマと出会わないために、予防対策は事前にしっかりととりたいものですね。
予防対策
- 山に入る場合は、ツキノワグマに自分の存在を伝えるため、クマ鈴やラジオなど、音の出るものを携行する
(クマの人身事故のほとんどは、クマと人がお互いの存在に気づかないまま、近距離で出会ってしまい、クマが人を恐れ、襲ってしまうことで起きています。クマは通常、人を避けて行動するため、自分の存在をクマに知らせることで、未然に事故を防ぐことができます) - クマの活動が活発になる早朝と夕暮れ時の外出を控える
- 万が一、ツキノワグマの遭遇に備えて、熊スプレーやナタなどを携行する
- クマの通り道となっている集落内の樹林の伐採や藪払い、草刈りをする
- 集落内の不要な果樹を伐採する
(もう誰も収穫しなくなった柿の木などを目当てに、クマが集落に下りてくることがあります) - ツキノワグマが出そうな場所を特定し、パトロールをする
(追い払いをする)
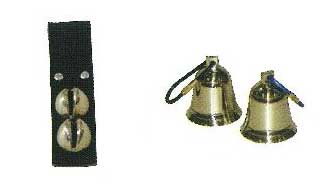
→商品リンク:クマ鈴
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-others

→商品リンク:熊スプレー
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-repellnent
余談となりますが、私は仕事柄、山に入ることが多いのですが、哺乳類等の生態調査中に、ツキノワグマに遭遇することがあります。
自然の中で、
- 赤
- 黄色
- 緑色
- 茶色
などはよく目にするのですが、真っ黒というのは、なかなか目にすることは無く、ツキノワグマはとても目立つ存在です。
漆黒の艶やかな毛並と、躍動する筋肉。
突然、目の前に現れると腰を抜かしてしまいそうですが、遠くで見ると“美しい”という印象を持ちます。
ツキノワグマが分布する本州・四国の都府県の約7割では、「絶滅のおそれのある野生生物」として指定しているのもまた事実です。
危険な動物という認識が強いために、問題になりがちなツキノワグマですが、一方で豊かな森林生態系を代表する動物でもあります。
遭遇・被害が出ないように、うまく付き合っていきたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ツキノワグマの生態など⇒
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-bear
★クマを追い払う、寄せ付けないには⇒
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-repellnent
★クマの侵入を防ぐには⇒
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-package
★クマを捕獲するには⇒
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-boxtrap-big
★クマの行動を確認するには⇒
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/bear-camera
この記事を書いた人
![]()
関連記事
投稿日:2023年10月12日
【熊被害2025】秋に増加するクマの被害に備えよう(主要都道府県クマ出没情報リンクあり)
投稿日:2023年9月1日
投稿日:2017年1月18日

ツキノワグマから田畑を守る~鳥獣被害対策の『講習会:クマ編』から~
投稿日:2016年5月19日

投稿日:2013年8月8日

先頭へ