豚熱・アフリカ豚熱の脅威から日本の畜産を守る!獣害対策の重要性と最新動向
投稿日:2024年6月10日
運営会社:株式会社 地域環境計画
投稿日 : 2019年04月02日
更新日 : 2024年06月10日

こんにちは、【鳥獣被害対策ドットコム】の井上です。
今回は、豚熱(CSF)(※旧:豚コレラ)対策として、効果的な防護柵の選び方・設置方法について整理しました。
柵を設置したからもう安全!
・・・そんなことはありませんので、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次

今回は、豚熱(CSF)に関連するイノシシ対策についてのお話です。
2018年9月に岐阜県各務原市で確認された豚熱(CSF)を発端に、現在では各地で豚熱(CSF)防除のための対策が進められています。
2019年7月現在でもいまだに事態は収束せず、農水省も被害拡大を防ぐための支援を強化する方針で施策と検討をはじめており、被害が相次いでいる愛知県、岐阜県を中心に、周囲の三重県、静岡県、富山県、長野県、石川県、福井県、滋賀県の7県でもイノシシ対策の強化が協議されています。
※2019年7月18日追記
7月16日に農水省は全国の地域を対象に、農場にイノシシの侵入を防ぐための防護柵を設置するための費用の半額を助成する旨を発表しており、より一層の対策の強化と早急な対応を全国の農場に求めています。
そもそも、今回の豚熱(CSF)発生については、「野生のイノシシが最初に感染し、県内の養豚場などに広がった」との見解もあります。
そのため、畜舎へのウイルス侵入を防ぐための水際対策の一つとして、畜舎周辺における“イノシシ対策”が重要であると言えます。
群馬県の高崎市では豚熱(CSF)発生した際の対策・対応についての講演会が開かれており、自治体は、農場に被害が出る前の情報共有と有事の際の迅速かつ的確な対応を呼びかけています。

さて、今回のテーマであるイノシシの侵入対策として効果の高い方法として、防護柵が用いられますが、防護柵は大まかに以下の4種類が挙げられます。
この中でも最も有効な手段として選ばれているのが、“ワイヤーメッシュ柵”です。
なぜ、ワイヤーメッシュ柵がイノシシ対策に有効かというと、
などが挙げられます。
ただし、ワイヤーメッシュを選ぶ際には、大まかに2つの注意点があります。
1つは線形の太さです。
ワイヤーメッシュの線形は、細いものでは3㎜以下もありますが、やはりこの太さでは強度面が心配です。
一般的にイノシシの侵入を防ぐためには、5㎜以上のものが推奨されています。
もう1つは、高さです。
イノシシは、意外とジャンプ力があり、低い柵だと簡単に飛び越えられてしまう可能性があります。
そのため、イノシシの侵入を防ぐためには、高さ1.2m程度のワイヤーメッシュが必要であるとされています。
また、イノシシ対策に特化したワイヤーメッシュ柵は、体サイズの小さなウリ棒(イノシシの幼獣)の侵入防止も防ぐことができるように、網目が細かく設定されているものもあります。
さらに、素材だけではなく、設置方法や設置する場所周辺の環境整備も重要です。
以下に、ワイヤーメッシュ柵を設置する際の効果的な設置方法をお伝えします。
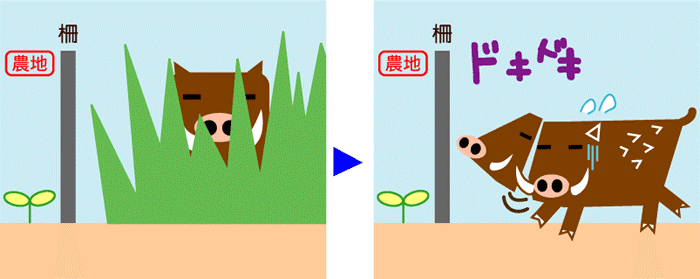
柵の周辺に広がる藪(やぶ)は、猪の隠れ場となり、猪は藪に隠れながら余裕を持って柵やその周辺を観察することができます。
また、藪に面した柵では、柵のまわりをうろつき、地面と柵との間に隙間ができている場所場を探し、そこから柵内への侵入を試みます。
ゆっくりと柵の探索をさせないためには、柵の外際の藪の刈り払いは重要です。
柵から3m程度は藪を刈り払うようにしましょう。
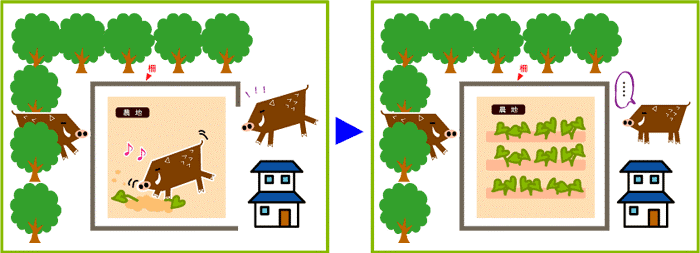
柵は、山際に面した場所のみ設置しても、猪は隙間を探して侵入しようとします。
そのため、田畑の周囲をしっかりと囲い、出入り口には扉も取り付けるようにしましょう。
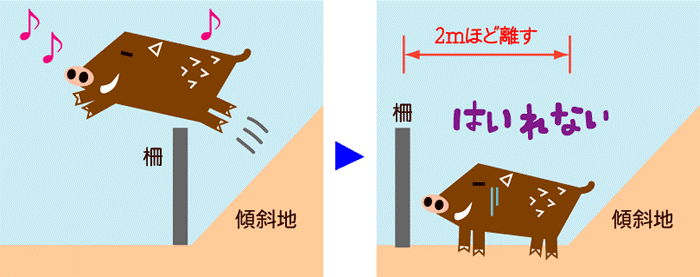
ワイヤーメッシュ柵を傾斜地のすぐそばに設置すると、いのししは傾斜地の上から柵を飛び越えてしまう可能性があります。
そのため、柵は傾斜地から2m程度は離して設置するようにしましょう。
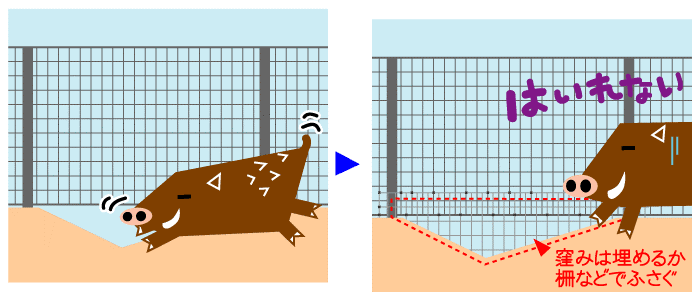
イノシシは、柵を飛び越えるよりも、潜り抜けることを優先します。そのため、柵と地面の隙間は必ずふさぐようにしましょう。
もし、くぼみを見つけたら、埋めるか、または柵でふさいでください。
また、地際をペグなどで固定することも効果があります。
※いのししは、地中の根などの餌を探す際、数十kgの石もひっくり返します。そのため、被害のあるところでは石でネット柵などの重しをしても効果がありません。
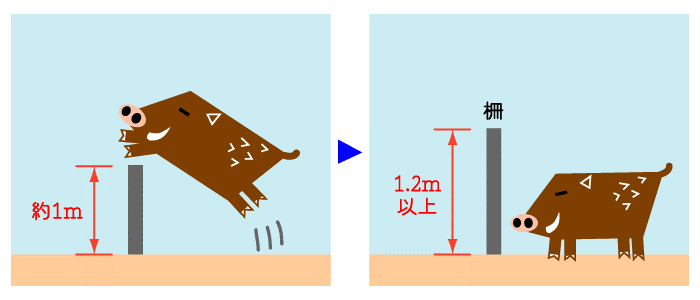
猪は1m程度の柵を助走なしで飛び越える跳躍力があります。そのため、柵の高さは、猪は1.2m以上を選ぶようにして下さい。
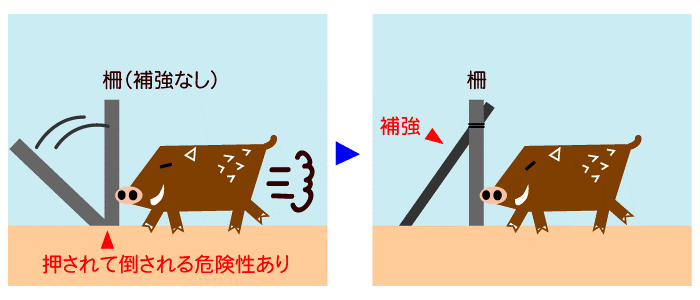
イノシシによる被害が大きな地域では、ワイヤーメッシュ柵の支柱だけではなく、斜めに補強用の支柱(筋交)を追加しましょう。
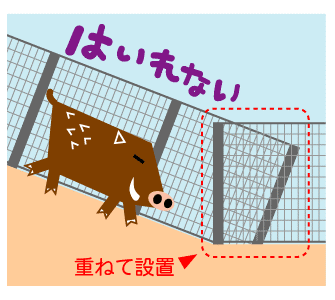
傾斜部や湾曲部などでは、ワイヤーメッシュ柵は、隙間ができないよう重ね合わせて設置しましょう。
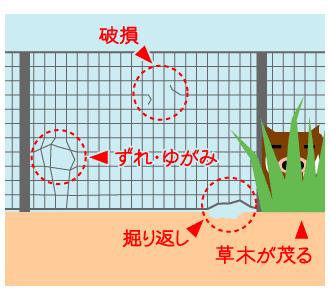
ワイヤーメッシュ柵の設置後には、定期的に柵の破損やずれ・ゆがみ、柵の地際の掘り返しなどの点検をするようにして下さい。
また、一度、柵を設置しても、最初から猪を完璧に防ぐのは難しいかもしれません。
地域の猪の動きに合わせて、少しずつ柵を改良していきましょぅ。
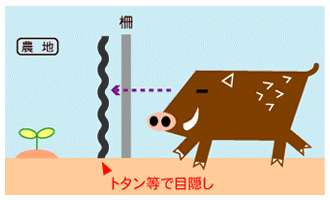
いのししは柵の内側が確認できないと、餌となる食物が見えなくなり、また柵の向こうが見えない不安から、柵を飛び越しにくくなります。
そのため、ビニールシートやトタン板を併用して、外からの中が見えないように目隠しをすると、被害防止の効果が上がります。
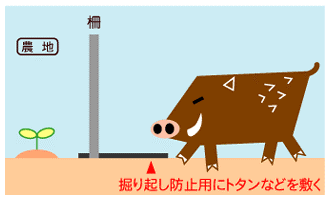
イノシシは、ワイヤーメッシュ柵と地面の隙間を探し、掘り起こして畑地に侵入しようとします。
そのため、柵の外側にトタンやワイヤーメッシュを敷くと、侵入防止効果が高まります。
さらに、サルが分布するような場所では、ワイヤーメッシュ柵の上部に電気柵を設置する複合柵が有効です。
イノシシ・シカ・サル対策用 防護柵【 おじろ用心棒 スプリング式】
ワイヤーメッシュ柵に限らず、イノシシ対策用の防護柵は、設置を済ませたら「これでもう安全」という、ものはありません。
イノシシが畜舎に執着していればいるほど、中に入ろうとする執念は高くなっていきます。
定期的な点検を行い、侵入しようとした痕跡を見つけたら、補強対策をするように心がけてください。
弊社としても、直近で増大しているイノシシ対策用防護柵の問合せ数からも問題の深刻性を受け止め、確かな情報を必要としている農場経営者の方々ひとりでも多くに届くよう情報発信を強化していくよう進めてまいります。
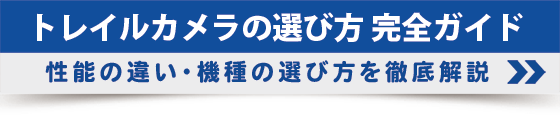
この記事を書いた人
![]()
豚熱・アフリカ豚熱の脅威から日本の畜産を守る!獣害対策の重要性と最新動向
投稿日:2024年6月10日
柵の補修・補強には、獣害柵補強用資材「モグレーヌ」がおすすめ!
投稿日:2018年6月6日
トレイルカメラ設置方法を工夫して「空うち」を減らす~失敗する設置例もご紹介~
投稿日:2018年3月9日
イノシシ柵のおすすめ!猪対策用ワイヤーメッシュ柵『いのししくん』 ~設置効果について現場を視察~
投稿日:2017年9月21日
投稿日:2016年3月2日
イノシシからみかん畑を守る!~ワイヤーメッシュ柵「いのししくん」を小田原のみかん農園に納品
投稿日:2015年12月8日

先頭へ